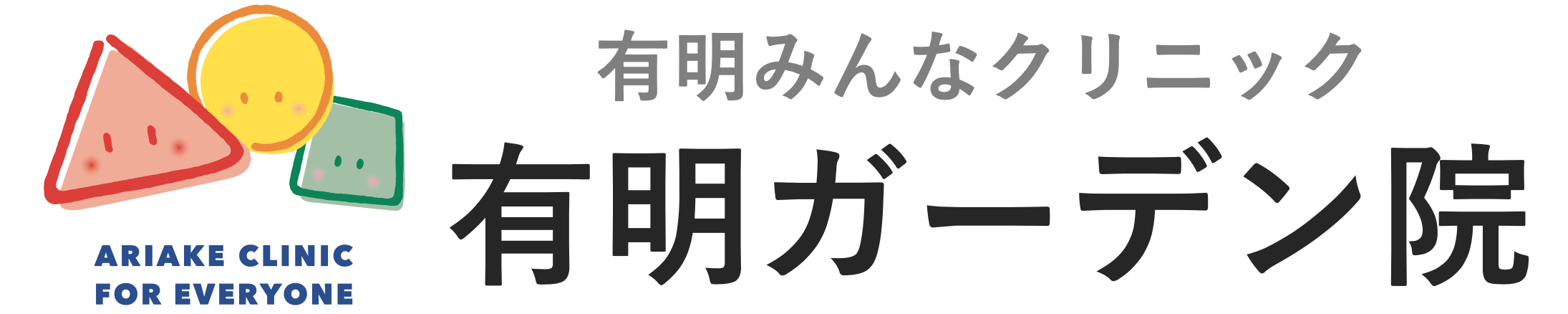2025.01.10 「理解に徹してから理解される」
本日は、「7つの習慣」の第5の習慣 「まず理解に徹し、そして理解される」 についての学びを共有します。
「理解に徹してから理解される」とは?
私たちは、日々の業務や患者様対応において、「自分の話を聞いてほしい」と思う場面が多くあります。しかし、相手に理解してもらうためには、まず相手の気持ちや状況を理解することが大切です。

発表で紹介された具体例
本日の朝礼では、クリニックの業務における「理解してから理解される」を実践するための具体例が紹介されました。
- 患者様対応の場面
例えば、患者様が待ち時間について不満を感じている場合、ただ謝罪するだけでなく、次のような対応を意識します:
お話をじっくり聞く:待ち時間が長くなった背景や、患者様が急いでいる理由などを尋ねる。
共感を示す:「お忙しい中、貴重なお時間をいただきありがとうございます」と気持ちを伝える。
状況を説明する:現在の混雑状況や対策を丁寧にお伝えする。
こうしたプロセスを経ることで、患者様の不安を軽減し、より良いコミュニケーションが生まれるとのことでした。
- 同僚とのコミュニケーション
日々の業務で、他のスタッフにお願いごとをする際も、「相手の状況を理解する」姿勢が重要です。
忙しいタイミングを避けて話しかける。
相手の負担にならない形で協力をお願いする。
感謝の気持ちをしっかり伝える。
これにより、スムーズな業務連携とチームワークの向上が図れます。
「理解すること」がもたらす効果
患者様との信頼関係が深まる
相手の気持ちに寄り添うことで、安心感を提供し、信頼関係が強化されます。
職場の雰囲気が良くなる
同僚の状況を理解することで、無駄な衝突を避け、チーム全体の働きやすさが向上します。
結果的に、自分の意図も伝わりやすくなる
まず理解する姿勢を持つことで、自分の考えや意見を相手が受け入れやすくなります。
最後に
「まず理解してから理解される」は、一見シンプルですが、実際に実行するには意識と努力が必要です。私たちクリニック全体で、この習慣を実践し、患者様や同僚との良好な関係を築いていきたいと思います。
皆さんもぜひ、日常生活やお仕事で「理解すること」を意識してみてください!次回のブログでも新しい学びを共有していきますので、お楽しみに!
クリニックのミッション:「笑顔で安心して子育てができる社会を創る」
これを目指して、スタッフ一同が一丸となって努力しています!引き続き、よろしくお願いいたします。